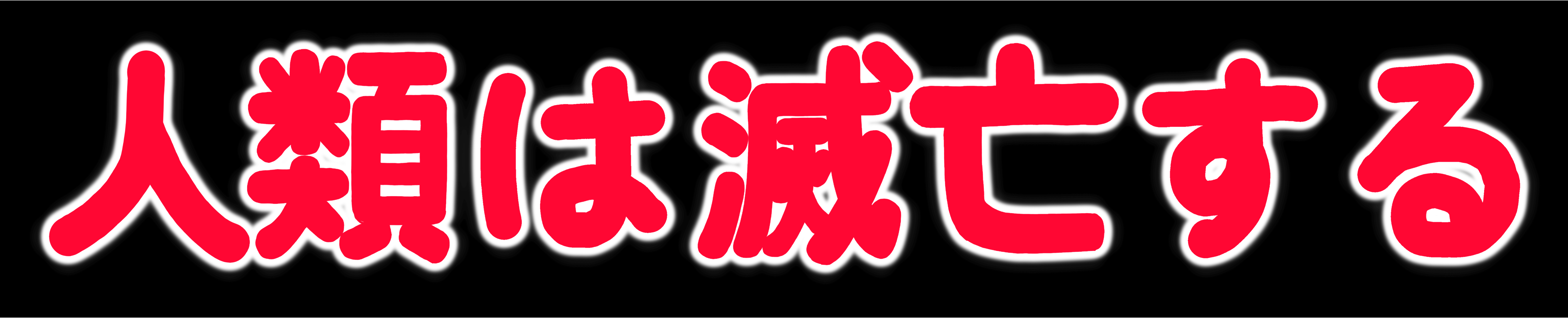南海底帝国の令嬢とその家族
ひとりのカニ人が、海底の砂を踏みしめ必死に走り逃げていた。周囲の仲間はひとり、またひとりと姿を消していく。捕まるまいと大きく腕を振るが、肩から下げた鞄に邪魔され、躓いてしまった。ああ、ダメだ。ここで自分の命は終わるのだ。だって、「かわいがり部屋」に入れられた者は、誰一人帰ってこなかった。中で何が行われているのかもわからない。何やら恐ろしい場所であることだけが、一族の記憶を介して伝わってくる。きっと正気を失うほどに、非人道的な場所なのだ。
「おとなしくしなさい。お前たちはジュゴン嬢様の糧となるのです」
揃いの制服を着た人魚たちが次々と仲間を集め、統率の取れた動きで特殊な籠の中へと放っていく。
「勢い余ってちぎってしまわないように気をつけなさい。後でわけてもらえるわ」 ひとりの人魚はそう言いながら、躓いたカニ人を慎重に、かつ虫けらのように籠に放り投げると、「ここらでやめにしておきましょう。生態系を破壊しすぎるのは良くありません」と他の人魚たちを制した。残ったカニ人たちは、「助かったカニ……?」と呟いた後、蜘蛛の子を散らすようにわっと逃げた。鞄を持ったカニ人は、そんな仲間たちを、籠の中からじいと見つめていた。
「こ、ここがかわいがり部屋カニか……?」
ぎゅうぎゅう詰めの籠から這い出たカニ人たちの第一声はそれだった。光源はひとつの薄暗い照明のみで、窓はない。大きなテーブルには繊細な刺繍の施されたテーブルクロスがかかり、その上にひとり分の食器が置かれている。扉はあるが、鍵がかかっている上、酷く重そうだった。
「恐ろしい部屋カニ……カニ人はここで食べられてしまうカニか?」
ひとりが怯えた声でそういうと、恐怖は途端に伝搬した。
かわいがり部屋から生きて帰った者はいない。その重みをずしりと胸に感じる。
「なんて運が悪いカニ……カニ人たちはたまたまあのあたりを調査していただけなのに……カニ……」
このカニ人たちは、村の中でも大規模な調査隊のひとつで、食料となる小魚の生息域を調査しているところだった。
「弱肉強食カニ……小魚は我々に食べられ、我々は人魚ちゃんに食べられるカニ……」
「でも、せっかく多くの食料となりうるものを見つけたのに、そのスケッチも持ち帰れないのは残念カニ」
ひとりのカニ人が、鞄を下げたカニ人に向かってそう言う。この鞄を下げたカニ人はスケッチ係だ。彼は肩を落とした。
「そうカニね……。残った隊員もいるとはいえ、あの状況では転送された記憶も曖昧だろうし、スケッチがないと……。それにこの画材もまだまだ使えるカニ」
スケッチ係は鞄から鉛筆や絵の具を取り出し、弄んだ。彼はついつい多くのものを持ってきてしまう性質だった。今回も、不必要な画材や、古いスケッチブックを持ってきてしまっていた。
「持ち物が多すぎカニ、もっと減らしておけば逃げ切れたかも……」
「もしもの話をしても仕方ないカニ、それにみんなカニ人より身軽なのに捕まっているカニ」
そんな話をしていると、重たそうな扉がぎいと音を立てた。騒がしくしていたカニ人たちは身を硬くする。
「今日のは随分とにぎやかね」
軽々と扉を開け優雅に泳いできたその人魚は、長い黒髪をなびかせ、肌触りのよさそうな布を身にまとっていた。つりあがった真紅の瞳は、カニ人でさえ見惚れてしまうほど美しい。一族の記憶が教えてくれる。彼女は南海底帝国の有力貴族のひとり、ジュゴン人魚であると。ああ、ここは本当に、「かわいがり部屋」なのだ!
「3匹ぐらいあの子達にもあげましょうか。それ以外はわたくしひとりで楽しませていただくわ」
ジュゴン人魚が艶かしく舌舐めずりをすると、カニ人たちは皆一様に震え上がった。が、同時にこんな疑問も抱いた。
「他の貴族仲間は呼ばないのカニ?」
そんなカニ人の素朴な疑問に対し、ジュゴン人魚は上品に笑った。「そうね、答えてあげましょう……こういうことはひとりで楽しみたいときもあるということよ」。次の瞬間には、尋ねたカニ人の四肢はばらばらになり、ふわりと水中に浮いた。
カニ人たちは必死に部屋の中を逃げ回り、壁を破壊しようとしたり、扉を開けて逃げようとしたり、隠れてやり過ごそうとしたりするも、全ては無意味だった。ジュゴン人魚は美しい所作でカニ人をちぎり投げ、喰らい、高笑いをした。皆が心のどこかでこう思っていた──自分はここで喰い殺される運命なのだ。その思いが希望を食いつぶしたとき、カニ人たちは彼女の胸鰭に粉砕された。
だがスケッチ係のカニ人だけは、最後まで希望を必死に抱いていた。もし自分が死んだとしたら、作品たちはどうなるのだろう? 自分の絵までもゴミのようにちぎり投げられてしまうとしたら、それはとても嫌なことだった。
テーブルクロスの中へ隠れ、利き手でない方を投げて惑わし、とにかく鞄を抱えて走った。意味はないが、そうするほかになかった。だがしかし、結局体力がつきた。彼らは人魚族の赤子にも劣る身体能力なのだ。
「よく逃げたわね。お前が最後の一匹よ。ほめてあげる」
ジュゴン人魚はカニ人にぐいと顔を近づけ、やさしい声でささやく。
「ま、待ってほしいカニ! せめて、せめてこの鞄だけは!」
カニ人は鞄を片腕でぎゅうと抱いて、祈るような瞳で人魚を見つめた。
「ああ、その鞄。気になっていたの。何が入っているのかしら?」
「スケッチカニ。これは村の財産カニ。お願いだから捨てないで、村にかえして欲しいカニ。絵に罪はないカニ……まあカニ人にも罪はないカニが」
「へえ、それちょっと見せてくださらない?」
カニ人の返事を待たず、ジュゴン人魚は器用に鞄を開け、中のスケッチブックを取り出した。そのスケッチブックの中には、今日の探検で見つけた小魚や、村の近くに生えている海草、そして仲間たちの姿や人魚族の調査スケッチなどがあった。ジュゴン人魚は感心したような顔でぺらぺらとスケッチブックをめくり、ある絵に目を留めた。
「あらこれ、シーラカンスじゃない。あの子こんなにかわいかったかしら? もっと凶悪な顔をしているのではなくって?」
彼女が気になったのは、シーラカンス人魚の調査スケッチだった。カニ人は素直に答える。
「実物そっくりに描いたらちぎってなげられるカニ」
「あっはっは! そうでしょうね! そういう子だもの。お前は面白いわね、素直で……気に入ったわ。ほかの絵も素敵だし」
「あ、ありがとうカニ」
カニ人は、今にも殺されるのではないかという緊張感と、絵をほめてもらえたことのうれしさで頭が混乱した。びくびくと反応をうかがうようにジュゴン人魚のほうを見つめると、彼女は心底楽しそうな笑顔で続けた。
「そもそも、カニ人をちぎって投げるなんて野蛮な……それがたまらないのだけど……とにかく、そういう流行も、もともとはあの忌々しい古代魚が生み出したものだものね。いいわ。気分が変わった。その絵は処分しないであげる。でも村にはかえさない」
「どういうことカニ?」
カニ人はこてんと首をかしげた。ジュゴン人魚は大きく目を見開き、興奮した様子でこう言った。「お前はわたくしの画家になるのよ!」。
それからというもの、スケッチ係のカニ人は、「宮廷画家」としてジュゴン人魚のもとで絵を描くようになった。目の回るような額の固定給、カニ人ひとりにはあまりにも広い邸宅とアトリエ、いままで触れたこともないような素材の調度品、すべてが彼にとって新鮮で驚きだった。ジュゴン人魚からの依頼だけでなく、他の貴族仲間や使用人からの依頼も彼は快く受けた。ただし、彼の正体は秘匿され、依頼も、直接依頼者に会わないで済む形のものしか受けることができなかった。ジュゴン人魚からの寵愛を受けた画家の正体がカニ人となると、外聞がよくないのだという。だが彼は幸せだった。村の中で過ごしていた時よりも幸せかもしれなかった。貴族は目が肥えていて評価者として申し分ないし、村では価値のないものとされた、非写実的な絵や、抽象的な絵も描くことができた。村のカニ人たちにとって、絵は地上で言う写真のようなもので、それにそぐわない物は無価値だった。
カニ人の邸宅の呼び鈴がなった。この呼び鈴を鳴らすのは、ジュゴン人魚ぐらいであった。
「カニ人、少しいいかしら」
「また依頼カニ?」
「いいえ、ちがうの。でもちがわないわね。頼みたい絵があるのは確かよ」
ジュゴン人魚は中に泳いでいくと、柔らかなソファにほとんど寝転がるようにして座った。
「どうしたカニ? 体調悪いカニ?」
「ええ、悪いわ。でもそうじゃないの。カニ人……お前を解雇するわ」
「解雇!?」
カニ人は驚いて飛び上がった。ジュゴン人魚は苦々しげに繰り返す。「解雇よ……解雇するしかないの」。どうやら望んでないことであるとはわかったが、それ以上がわからなかった。なぜ自分が解雇されるような羽目になったのか?
「どうしてカニ? カニ人の絵に不満があるカニ?」
「いいえ、お前の絵はすばらしいわ……でも……絵に不満があるわけじゃないのよ。だけど、本当の理由は言えないわ。お前たち、一族で記憶を共有しているんでしょう」
「たしかにそうカニが、一族にとって超重要事項じゃない限り、こんな細かい会話の内容までは共有されないカニよ。そんなことしたらパンクするカニ」
「ふふ……残念だけど、わたくしがこれから言うことは、きっと重要事項だわ」
「それを聞かないまま、ここにいることはできないカニ?」
「できないわ。ねえ、すぐにお前を追い出さずこうして説明している理由はおわかり?」
カニ人は少し考えたがわからなかったので、素直にそう答えた。するとジュゴン人魚は、自嘲的に笑ってから彼に向き直った。
「お前は一族かわたくしか、選ばなくてはならないわ」
カニ人は広いアトリエで、深く深く考え込んでいた。ジュゴン人魚はどうみても本気だった。「一族かわたくしか」。彼は記憶と今までのスケッチをたよりに、彼女の絵を描き始めた。悩んだときは手を動かせば、道が見えてくることがある。
滑らかに躍動する黒髪。豪華ではあるが、決して下品ではないシックな装飾の数々。艶かしくも威厳のある幻想的な身体。一族か、彼女か。
ここにいれば広い家で何不自由なく生活できるし、自由に絵が描ける。しかし、一族を裏切るなんてことは……。彼は悩みすぎて熱が出そうになるほどに悩んだ。それでも手を止めなかった。この絵を完成させたとき、きっと自分の本心がわかるはずだと信じていた。
一方ジュゴン人魚は、カニ人の邸宅から戻った後、自室ですぐ横になった。
「わたくしを選んでくれるなら、どうしても、一枚だけでいい……頼みたい絵が」
そう呟いて自らの腹をさする。彼女はとうとう耐えられなくなって、声を殺して泣き出した。
「ジュゴン嬢様……」
そんな彼女に、侍女の人魚がそっと寄り添う。ちなみに侍女というのは、カニ人たちを捕らえたときに指示を出していた、あの人魚である。
「ああ、お前はどう思う? あのカニ人はわたくしを選ぶと思う?」
「らしくないですわ、ジュゴン嬢様。間違いなくジュゴン嬢様を選ぶに決まっておりますわ」
侍女はそう言って、優しく自らの主を撫でた。ジュゴン人魚は心地良さそうに目を閉じる。
「あのカニ人に与える情報は、慎重に選んできました。幸いあれは頭が弱いですから、特に詮索してくることもありませんでしたが……。とはいえ、ジュゴン嬢様を裏切った者を、おいそれと村に帰すわけにはいきません」
ジュゴン人魚は腫れぼったくなった目を開き、じいと彼女を見つめた。彼女の硬く結ばれた唇は、主のためならどんな汚れ役にもなるという、忠誠心のあらわれだった。ジュゴン人魚はゆっくりと目を細め、何か悪い考えを振り払うように瞬きをした。
「そうならないことを祈っているわ」
カニ人は数日の後、ジュゴン人魚を自らの邸宅に呼んだ。
「一族かわたくしか、決めたのかしら」
「決めたカニ。これを見て欲しいカニ」
カニ人はキャンバスにかけていた布をやさしく取り去った。その裏にあったのは、悩みながら描いていた、あのジュゴン人魚の絵だ。正確に言うと、ジュゴン人魚を描いているカニ人自身の自画像がそこにあった。
「カニ人はジュゴン人魚ちゃんを選ぶカニ。今まで密偵という体で一族とのつながりを保っていたカニが……どのみち記憶は薄れてきていた、つまり、すでに誤魔化しがきかないところまで来ていたカニ。戻って裏切り者として制裁されるよりは、このままジュゴン人魚ちゃんの画家でいる方が、都合がいいカニ」
カニ人は少し照れ臭そうに顔を背ける。ジュゴン人魚は絵を見つめ、たまらない気持ちになって、彼をやさしく抱きしめた。
「ああ、お前は本当に、最高の画家ね! この絵はつまり、一生わたくしの画家でいると、わたくしに忠誠を誓うと、そういうことでしょう?」
「誠に不本意カニがそうなるカニ」
「不本意? あまり無礼な物言いをすると、お前といえどもちぎってなげてしまうわよ」
「ひっ……」
カニ人が胸鰭の中で力なく震える。ジュゴン人魚は嬉しそうに笑った。
「ああ、よかった。これでお前を殺さずに済むわ」
「……カニ?」
カニ人の震えが止まった。
「あらお前、一族を選べば村に帰れると思っていたの?」
彼女は悪戯っぽく笑い、固まってしまった彼をふわりと水中に投げる。
「『かわいがり部屋から生きて帰ったものはいない』、お前たちが言っていたことじゃない」
ジュゴン人魚が頼みたい絵というのは、家族の肖像画だった。
「わたくし、子供ができたのよ。人間との子供よ。純粋な人魚なら赤子でも強いけど、人間の血が混ざっているから……お前の一族に狙われて、殺されてしまったらたまらないわ」
「それで二択を迫ったカニね」
「そうよ。でもお前はわたくしを選んでくれた……これで安心して依頼ができるわ。わたくしの子供が生まれたら、わたくしと、子供と、そして夫の絵を描いて欲しいの。ただ、夫は人間だから、海の中には来れないわ。直接会いに行っていいから、想像で構わない、3人そろった絵を……お願い」
彼女は最後まで言い切ってから、ゆっくりと自らの腹をさすった。その中に命が宿っていることを知ったカニ人は、生命の根源的な喜びに触れたような気分になった。子が生まれる! それはたまらなくよいこと、美しいことのように思えた。
「任せるカニ! 最高の絵にしてみせるカニ」
「頼りにしているわ」
ジュゴン人魚はやわらかく目を細めた。普通のカニ人であれば、彼女のこんな表情を見ることは一生かなわないだろう。彼は誇らしい気持ちになり、彼女を選んだのは正解だったと思った。自分にはこんなにもすばらしい絵を描かせてくれる主がいる、その事実が彼を高揚させた。その主がしばしば同族をちぎって遊んでいるのは恐ろしい話だが、それさえも彼女への忠誠心への糧となっていた。飴と鞭は、両方与えるから意味があるのだ。
カニ人は少し浮き足立った様子でジュゴン人魚の自室へ向かい、重い扉をノックした。しばらく待つと、本人がゆっくりと扉を開け、カニ人を見てたまらなく嬉しそうな顔をした。
「ジュゴン人魚ちゃん、体は大丈夫カニ?」
「大丈夫よ」
「そうカニか。絵、やっと描けたカニよ。見にくるカニ?」
「ありがとう。もちろん見に行くわ。ずっと楽しみにしていたもの……そしてその後、この世で一番上等な枠にいれさせるわ」
カニ人はまだ本調子ではない彼女に配慮し、ゆっくりとした足取りで、彼女を案内した。広いアトリエに堂々と鎮座するその絵は、彼の体よりもずっと大きい。
「素晴らしい出来カニ。自信作カニ」
絵の中のジュゴン人魚は、目を細めてやさしく微笑んでいる。心から信頼している者にしか、見せることのない顔だ。その隣では人間の男が、彼女に視線を向けている。そして彼の腕の中では、愛らしい赤子が、ちいさな尻尾の先を咥えて眠っている。ふたりの子供だ。
この子が産まれたとき、部屋にはジュゴン人魚とその侍女、そしてカニ人だけだった。「赤ちゃんって、こんなに小さいカニか。体に対して尻尾がすごく長いカニ」とカニ人がこぼした横で、ジュゴン人魚は産みの苦しみと感激とでぼろぼろ泣いていた。「この子の名前、ずっと前からあの人と一緒に決めていたの。この子はヨナタマ。わたくしのいとし子」。赤子は1日母親と過ごした後、侍女の手によって、誰にも見つからないように父親の元へ連れて行かれた。彼女は侍女に子供を預けながら、「別れがこんなにつらいとは思っていなかった。ああ、1年以上も一緒にいたのに」と呟いた。
ジュゴン人魚はしばらく感傷に浸った。それが済むと、「タイトルは何かしら」とおもむろに尋ねた。それに対し、カニ人は極々シンプルな答えを返した。「変に気取るより、そういうシンプルなものがいいわ。この絵は家族の絵で、それ以上でもそれ以下でもないもの」。彼がつけたタイトルはこうだった──
《南海底帝国の令嬢とその家族》。
Novel's by みえ様
小説TOPはコチラカニ。